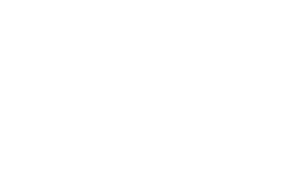太宰治の短編集。
借金まみれ、酒まみれ、おまけに女にもだらしないという放蕩男、大谷穣治(浅野忠信)と、そんな夫を献身的に支える妻、佐知(松たか子)。
夫は行きつけの飲み屋「椿屋」から金を盗んだ。
店主夫婦に、家まで乗り込まれ返済を迫られます。開き直った夫はナイフを振り回し、言いがかりをつけた。みかねた妻が謝罪し、事情を聞き、返済を約束した。けれど、夫がお金を入れるわけもないのだから家計は火の車だし、目途があるわけでもない。
仕方がないので、妻は思い付きでウソを言い、その店で働かせてもらいお金を返すこととなりました。
そうしていれば、店に通う亭主にも会えるからと、嬉しそうに、けなげに言います。
美人な妻は、途端に人気者となり店は繁盛した。
お客さまから、チップをいただくことで生活のめども立ち、自分の美しさが、お金になることがわかり、仕事の楽しさも覚えます。
楽しそうにする妻に嫉妬をおぼえた夫は、妻を慕う常連客の岡田にやきもちを焼き、妻の自分への愛情を試すために、岡田を家に連れ込み泊まらせる。
岡田は、佐知への気もちが抑えきれずに夜明けにキスをしてしまうのです。寝ていたはずの夫はそのことに気づき家を出てしまいます。
そうなるように仕向けておいて傷ついてしまう夫。
元もと、死にたくて仕方がなかった夫は、自分に惚れ切っている女、飲み屋のママ、秋子を道連れの相手にえらび心中するも未遂に終わる。
殺人未遂の容疑者にされた夫を救うために佐知は捨て身の覚悟で弁護士になった昔の男に会いに行く。
そして・・・
これは果たして献身なんだろうか。愛とは、生きるとはどうあることなのでしょうか。
「私たちは、生きてさえいればいいのよ」とつぶやく妻。
戦後間もない時代のお話ですから、今の感性にはなかなか響きづらいのかもしれませんが、愛した人に裏切られ続けてもなお、夫を守り抜く姿勢に心が打たれます。
切ないけれど、どうしようもないものをまるごと受け止めて、生きることを肯定した映画。
実際に太宰は自殺してしまう訳ですから、生きることの苦しさを抱えている苦悩がリアリティを伴って表現されていて、胸がしめ付けられます。
どうしようもない男に惚れてしまう女の心理ってなんなの。
惚れた男だとはいえ、家庭を顧みず、よそに女を作りそしてその女と心中することを選ぶ。
未遂に終わったとはいえ、夫を救うことに生きがいを感じてしまうのはなぜだろう。素直で純情だということだけで、まかり通るのでしょうか
他者の存在の中でしか生きられない共依存的なものがあるのではないでしょうか。
映画の中には、原作では語られていない、大谷を捨てて幸せになれるかもしれない男性があらわれるのに、夫を助けるために捨て身で彼に救いを求めに行く姿がいじらしいのか、アホなのか。